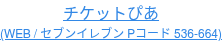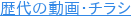「式能」は、昭和20年に能楽協会設立後、昭和36年に第一回が行われ、以降毎年、翁附五番立(江戸時代の基本的番組編成)にて開催しており、本年で66回目を迎えます。
現在、シテ方五流が一同に会する翁附五番立の能楽公演としては、唯一の大変貴重な催しです。
今回はシテ方金剛流宗家・金剛永謹が「翁」を勤めます。
能楽の正式な上演形態である翁附五番立は、江戸時代に「武家式楽」として確立され、能楽以前の予祝芸能である「翁」から始まり、『神・男・女・狂・鬼』のジャンル分けに従って上演されます。また能の間には中世の大名・小名や庶民を描く狂言を挟み、人間の様々な笑いが演じられます。
1日を通して能楽を鑑賞する事で「過去・現在・未来」更には「神・人・仏」を知ることになります。能楽は、人や文化の多様性を認め、様々な民族文化を内包した総合芸術といえます。
令和8年2月15日(日)
【第一部】10:00開演
【第二部】15:30開演
国立能楽堂
開催概要
第66回 式能
- 日時
- 令和8年2月15日(日)
第一部 10:00開演【9:15開場】~14:40(予定)
第二部 15:30開演【第一部の入れ替えが終わり次第の入場】~19:25(予定)
※第一部・第二部入替制 - 主催
- 公益社団法人能楽協会
東京都/公益財団法人東京都歴史文化財団/江戸東京伝統芸能祭実行委員会
- 協賛
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 後援
- 中央区/中央区教育委員会/一般社団法人中央区観光協会
- 会場
- 国立能楽堂
- 「翁」開演後「高砂」開始までは見所へのお出入りを一切お断り致します。
- 第1部終演後は、見所整備の為、通し券のお客様も一旦ご退場頂きます。
- 第2部ご入場は、見所整備終了後のご案内となります。
- 上演中の撮影、録音、録画は固くお断り致します。
- 上演中はアラーム、携帯電話、電子端末などの電源はお切り下さいますようお願い致します。
- ほかのお客様のご迷惑や上演の妨げとなる行為はご遠慮願います。
- 出演者はやむを得ぬ事情により変更させて頂く場合がございます。
- 開場前のご来館につきましては能楽堂館外にてお待ち頂くことになりますのでご承知おき下さい。
- 再入場は可能ですが、必ずチケットの半券をお持ちいただき、再入場の際にご提示をお願いいたします。
チケットの半券をお持ちでない場合、再入場は出来ませんので、予めご了承ください。 - 当日は主催者、及び関係者・メディアの撮影が入る可能性がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承下さい。
- 鑑賞
サポート - 本公演では、曲目解説の英語版を無料でご用意致します。公演当日、主催者受付にお声がけ下さい。なお、数に限りがございますので予めご了承下さい。
English version of the commentary of the plays will be available at the venue.
Please feel free to ask the staff at the reception desk.
チケット情報
入場料金(全席指定)
| 1・2部通し (正面) | 14,500円 |
|---|
| 1・2部通し (脇正面・中正面) | 9,500円 |
|---|
| 1部(正面) | 8,500円 |
|---|
| 1部(脇正面・中正面) | 6,000円 |
|---|
| 2部(正面) | 8,500円 |
|---|
| 2部(脇正面・中正面) | 6,000円 |
|---|
| 学生席(26歳以下) 詳細はこちら※外部サイトに遷移 | 1,200円 |
|---|
- お受取り・お支払い方法によって、別途手数料がかかる場合がございます。
- 障害者割引あり(対象は脇正面後方席です。枚数に限りあり)。ご本人のみ一般価格の2割引き(学生席は割引対象外)。能楽協会でのみ販売(お客様ご自身がぴあ、カンフェティで直接購入されたチケットは割引対象外です)。必ず2月10日までにお電話にてお申し込み下さい(電話:03-5925-3871<平日10-16時受付>/12月12日午前10時受付開始)。チケットは公演当日のお引替えとなります(要障害者手帳提示)。なお、事前にお申込みのない方への割引は致しかねますので予めご了承下さい。
- 本公演は未就学児のご入場をご遠慮頂いております。
一般販売
☎カンフェティ 050-3092-0051
(有人対応 平日10:00-17:00)
- 前売りチケットは令和7年12月12日(金)午前10時~令和8年2月11日(水)までの販売となります。
- 2月11日(水)を過ぎてからのチケットのご購入については、当日券になります。
- 販売期間にかかわらず、チケットが売り切れ次第、販売を終了させて頂きますので予めご了承下さい。
第一部
-
能
金剛流翁 -
- 出演者
翁 金剛永謹 笛 森田保美 三番三 大藏教義 小鼓 大倉源次郎 千歳 吉田信海 脇鼓 田邉恭資 脇鼓 清水和音 大鼓 柿原弘和 太鼓 上田慎也
- あらすじ
- 露払いの千歳の舞の後、五穀豊穣、天下泰平を祈る白い翁の静謐な舞。大地を踏みかため、精霊を呼び起こす黒い翁の躍動的な舞。素袍大紋、侍烏帽子で威儀を正し、舞台披きや年頭に舞われる儀式的な一曲。
-
能
金剛流高砂 -
- 出演者
シテ 金剛龍謹 笛 森田保美 ツレ 宇髙徳成 小鼓 大倉源次郎 ワキ 福王和幸 大鼓 柿原弘和 ワキツレ 矢野昌平 太鼓 上田慎也 ワキツレ 村瀬慧 アイ 善竹大二郎
- あらすじ
- 阿蘇宮の神主友成は旅の途中高砂の浦で、松の木陰を清める老夫婦に相生の松の謂れを尋ねた。老夫婦は自分達こそ相生の松の精だと明かし姿を消した。友成が住吉に行くと住吉明神が現れ颯爽と舞を舞い千秋万歳を祝うのであった。
-
狂言
大蔵流佐渡狐 -
- 出演者
シテ 大藏彌太郎 アド 小梶直人 アド 大藏彌右衛門
- あらすじ
- 佐渡と越後の百姓が年貢を納めに都へ行く途中、「佐渡に狐がいるか」で賭けをする。佐渡の百姓は実は狐を知らず、賄賂を渡した奏者(役人)の助けもあって「佐渡に狐はいる」と判定され、賭けに勝つ。しかし、判定を不審に思った越後の百姓に狐の鳴き声を尋ねられ…。
-
能
喜多流清経 -
- 出演者
シテ 大村定 笛 熊本俊太郎 ツレ 内田成信 小鼓 鳥山直也 ワキ 宝生欣哉 大鼓 守家由訓
- あらすじ
- 平清経は豊前の国柳が浦にて入水自殺してしまったので、身内の淡津の三郎は形見を持って清経の妻を訪ね、その死を報告する。その夜の妻の夢に清経が在りし日の姿で現れ、自分の死に至るまでの物語を語る。
-
狂言
和泉流舟ふな -
- 出演者
シテ 野村萬 アド 野村万蔵
- あらすじ
- 主人と太郎冠者が外出の折、神崎の渡しという大きな川にさしかかり、太郎冠者が「ふな」と言って渡し舟を呼ぶ。主人は、舟は「ふね」と呼ぶべきだと言い争いになり、二人は和歌や謡を引き合いに出して自分の正しさを主張する。
第二部
-
能
観世流
杜若 恋之舞 -
- 出演者
シテ 藤波重彦 笛 藤田朝太郎 ワキ 村瀨提 小鼓 幸信吾 大鼓 國川純 太鼓 大川典良
- あらすじ
- 三河の国八橋で旅の僧が杜若の花に見とれていると、一人の里女があらわれ、在原業平の歌を引きつつ「伊勢物語」の故事を物語る。やがて女すなわち花の精は、和歌の功徳を讃美し、たおやかに〈序ノ舞〉を舞う。
-
狂言
大蔵流文荷 -
- 出演者
シテ 山本東次郎 アド 山本則秀 アド 山本則孝
- あらすじ
- 主人から文を届けるよう命じられた太郎冠者と次郎冠者はどちらも仕事を押し付けあい、仕方なく竹に文を結び付けて二人で担いで行くことにする。文の中身が気になった二人は読んでいるうちに、文を破いてしまう。
-
能
金春流放下僧 -
- 出演者
シテ 櫻間金記 笛 成田寛人 ツレ 伊藤眞也 小鼓 久田舜一郎 ワキ 飯冨雅介 大鼓 亀井洋佑 アイ 野村万之丞
- あらすじ
- 父の仇を討つため小次郎は僧籍の兄を説得し大道芸人の放下僧になりすまして、敵の利根信俊に近づく。曲舞・羯鼓・小歌などの様々の芸を演じて見せ、隙をうかがって仇を討つ。こきりこなど田楽芸の面白さ。
-
狂言
和泉流因幡堂 -
- 出演者
シテ 石田幸雄 アド 深田博治
- あらすじ
- 大酒呑みで悪妻ぶりに嫌気がさした夫は妻に離縁状を送り、因幡堂で新しい妻を授かるように願う。怒った妻は眠っている夫の枕元で「西門に立っている女を妻に」と囁く。それを夢のお告げだと信じた夫は西門に立つ女を妻にしようとするが、実は女は元の妻で…。
-
能
宝生流小鍛冶 白頭 -
- 出演者
シテ 佐野登 笛 栗林祐輔 ワキ 大日方寛 小鼓 森澤勇司 アイ 高野和憲 大鼓 内田輝幸 太鼓 徳田宗久
- あらすじ
- 三条小鍛冶宗近は剣を打って奉れとの勅命を受けたが、しかるべき相槌を打つものがいないのに困り稲荷明神に祈願に出かける。 現れた童子に激励され、帰宅して準備を整えて待つと霊狐が現れて相槌を勤め、無事名剣を仕上げる。
観能のてびき
初めての観能(能を観ること)でもかしこまらずに楽しめます。どうぞ、能楽堂にお越しください。
前日まで
- 演目について調べよう
演目のあらすじを読んでおきましょう。また、 能楽辞典を是非ご活用ください。
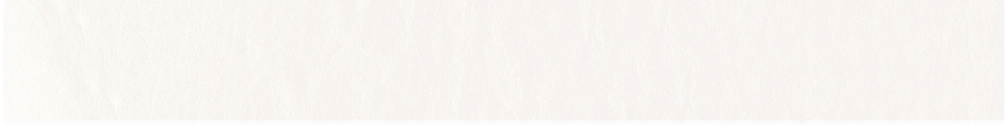
当日
- 観能時の服装について
特に決まりごとはありません。ご自分にとって着心地の良い服でお越しください。お着物の方もいらっしゃいます。後ろの人の視界の妨げになるような髪型や髪飾りは、ご遠慮ください。また、帽子等は客席ではお取りください。
また、短パン・サンダルなど露出の多い服装はお控えください。
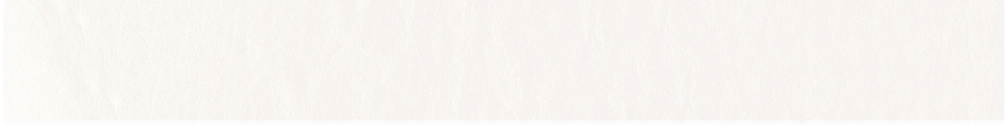
- 携帯電話・スマートフォン
開演前に電源をお切りください。
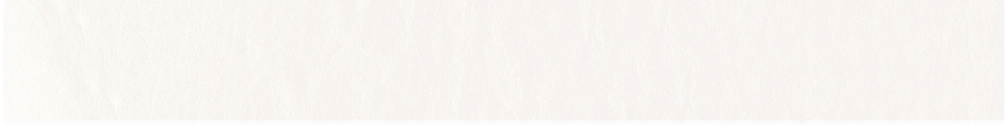
- 写真撮影・録音・録画
上演中の関係者以外の写真撮影・録音・録画は厳禁となっております。
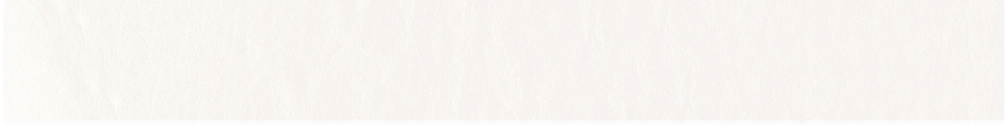
- 飲食について
客席での飲食はご遠慮ください。飲食は上演前や、休憩時間にロビーでお楽しみください。晴天の場合は、中庭や前庭のベンチ等をご利用頂けます。なお、ロビー内の席、ベンチの数には限りがございますこと、予めご了承ください。
能楽堂内のレストランの詳細はレストラン「お食事処 ひまわり」へ直接お問合せください。当協会で詳細は分かりかねます。レストラン「お食事処 ひまわり」
電話 03-5410-2611
ホームぺージ https://www.ntj.jac.go.jp/nou/facilities/shop/#shopHimawari
能楽堂内に自動販売機はありません。能楽堂の門を出て正面右のビル前に自動販売機はあります。(2025年2月現在)
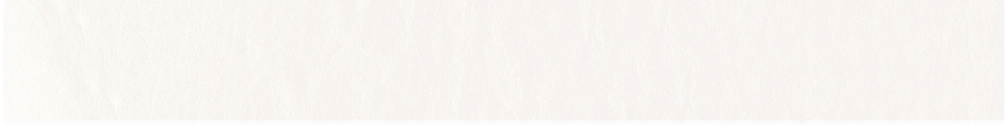
- 舞台に集中
公演が開始されましたら、能の世界を堪能してください。
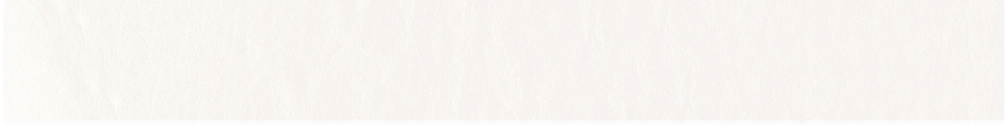
能楽情報メルマガにご登録ください
能楽に関する情報や公演情報を月一回程度メールにてお届けします。